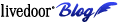2016年06月18日
教えの立場
領収証を整理していると、本屋のレシートが少ないのを実感します。
本当に本を買わなくなってしまったんだなぁ、と。
ここ最近は語学関連は購入することがあっても
それ以外は少ないみたいです。
もっと本を読みたい気持ちはあるんですが、
どうも手に取ることが減っている感じ。
移動の新幹線や飛行機の中でも本を読むより
睡眠で体を休めようとするのも関係しているかもしれません。
そんな中でも買って読むことがあるのが、仏教関連の本です。
本格的な仏教書を読むわけでもなく、
かといって僧侶が書いた仏教的生き方のような本でもなく、
仏教全体の概説や、各宗派の位置づけの違いなどについて知っていくと
歴史的な観点からも面白いものだと感じています。
状況に応じて、相手に応じて、時代に応じて、
教えの趣旨が異なっているのでしょう。
そのあたりが宗派の違いとして表れているのかもしれません。
何を意図して、誰のために、どういうサポートをしようとしたか。
その観点で見ると個性の違いにも納得できる気がしますし、
内容は違えど「教える・伝える」ことを仕事にしている僕個人としても
スタンスを柔軟にして対応するヒントが得られそうです。
生活環境として厳しい時代に生まれた教えには
多くの人を苦しみから救うスタンスがあるように見受けられますし、
教えを信じることの比重が大きいように感じます。
一方、日常を離れて修行するようなスタンスでは
その非日常のコミュニティに属すための特殊な流儀があったりする。
僕がコミュニケーションや心理を学んできた過程でも
修行的にトレーニングする側面を好んでいたせいか、
仏教関連の本を読んでいても修行が強調されたものに
何か惹かれるところがあるみたいです。
特に、禅と呼ばれる流派は、本質へ一気に迫ろうとするように思えるので、
シンプルに重要なエキスを濃縮したようなトレーニングを好む僕には
違う分野ながらも教わるところや賛同するところが多いようだと感じます。
禅というと、いわゆる禅問答や座禅が有名だと思いますが、
いずれにしても仏の教えを頭で理解して知っているのではなく
心と体でどのように納得していくかを狙ったものだそうです。
それだけ実践の側面が強く、仏教を学ぼうとする人たちと
立ち位置の違いを強調したかったところがあるみたいです。
元々インドで生まれた仏教が中国に伝わってきたときに
経典が伝わってくる順序や脈絡がズレてしまったことから
教え同士の関連性を調べたり、全体像を整理したりする動きがあったんだとか。
するとどうしても客観的で知的な理解になりやすかった。
それに対する実践的な立ち位置として禅が生まれた。
そんな話を読みました。
だからなのか、ちょっと過激なユーモアも含まれているらしく
「シッダールタ(釈迦)の言葉をあれこれ解釈するのは
シッダールタが尻を拭いた紙を後生大事にするようなものだ」
みたいな表現さえあるらしいです。
カリスマの言葉をありがたがって自らは実践しようとはしない
…そういうのはどの分野にもあるもののように見えますが、
仏教の伝統の中にもあった話なんでしょう。
と同時に、禅にこのようなスタンスが表れるのは
言葉では理解できないところを伝えようとするからでもあるようです。
言葉を通してでは、どうしても頭で知的に理解しようとしてしまう。
もっとストレートに、言葉以外の部分で伝授していく部分が大きい。
だからこそ頭で考えようとしても無理のある禅問答を出したり、
言葉を止めて座るなかで体得していく座禅をしたりする、と。
この辺もコミュニケーションのトレーニングで重要になる部分だと感じます。
言葉ではないところで伝わるものが大きな違いを生みます。
しかしながら、言葉ではないところでの伝達は
それ相応の関係性やトレーニング量が関わるのでしょう。
ある程度の覚悟が必要なようです。
気軽に学んで、すぐに自分の課題が解決して、悩みのない日常に戻る…
そういう種類のものではありません。
そこで面白いのが、禅宗で修行の道に足を踏み入れるときには
儀式として「一度、断られる」ステップが入る、ということ。
覚悟を試すとも言えますし、心理学的には
修行のコミュニティに入るための通過儀礼だともいえます。
よく芸人や落語家が弟子入りするときに
師匠の家の前で一日中待っている、なんて話がありますが
断られても「そこを何とか」と粘るような時間を体験するらしいんです。
もちろん、このハードルの高さが修行を続ける覚悟を磨くにも役立つのでしょうし、
弟子をある程度は選抜するような効果もあるのかもしれません。
ただ僕の印象としては、それ以上に
そこまで大変な思いをしなくても大丈夫じゃないか?
と示唆してくれている部分もあるように感じました。
修行の末に苦しみから解放されるとしても、
いずれは何かしらの形で日常に戻っていくわけです。
だったら早いうちに苦しみを楽にして日常に戻ったって良いだろう。
わざわざ大変なところにいかなくても良いのでは?
そんな配慮も含まれているような気がしました。
やみくもに広げようとするのではなく、教えが必要な人に届くようにする工夫。
そのあたりにも「教える・伝える」立場として学ぶところがあるように感じています。
本当に本を買わなくなってしまったんだなぁ、と。
ここ最近は語学関連は購入することがあっても
それ以外は少ないみたいです。
もっと本を読みたい気持ちはあるんですが、
どうも手に取ることが減っている感じ。
移動の新幹線や飛行機の中でも本を読むより
睡眠で体を休めようとするのも関係しているかもしれません。
そんな中でも買って読むことがあるのが、仏教関連の本です。
本格的な仏教書を読むわけでもなく、
かといって僧侶が書いた仏教的生き方のような本でもなく、
仏教全体の概説や、各宗派の位置づけの違いなどについて知っていくと
歴史的な観点からも面白いものだと感じています。
状況に応じて、相手に応じて、時代に応じて、
教えの趣旨が異なっているのでしょう。
そのあたりが宗派の違いとして表れているのかもしれません。
何を意図して、誰のために、どういうサポートをしようとしたか。
その観点で見ると個性の違いにも納得できる気がしますし、
内容は違えど「教える・伝える」ことを仕事にしている僕個人としても
スタンスを柔軟にして対応するヒントが得られそうです。
生活環境として厳しい時代に生まれた教えには
多くの人を苦しみから救うスタンスがあるように見受けられますし、
教えを信じることの比重が大きいように感じます。
一方、日常を離れて修行するようなスタンスでは
その非日常のコミュニティに属すための特殊な流儀があったりする。
僕がコミュニケーションや心理を学んできた過程でも
修行的にトレーニングする側面を好んでいたせいか、
仏教関連の本を読んでいても修行が強調されたものに
何か惹かれるところがあるみたいです。
特に、禅と呼ばれる流派は、本質へ一気に迫ろうとするように思えるので、
シンプルに重要なエキスを濃縮したようなトレーニングを好む僕には
違う分野ながらも教わるところや賛同するところが多いようだと感じます。
禅というと、いわゆる禅問答や座禅が有名だと思いますが、
いずれにしても仏の教えを頭で理解して知っているのではなく
心と体でどのように納得していくかを狙ったものだそうです。
それだけ実践の側面が強く、仏教を学ぼうとする人たちと
立ち位置の違いを強調したかったところがあるみたいです。
元々インドで生まれた仏教が中国に伝わってきたときに
経典が伝わってくる順序や脈絡がズレてしまったことから
教え同士の関連性を調べたり、全体像を整理したりする動きがあったんだとか。
するとどうしても客観的で知的な理解になりやすかった。
それに対する実践的な立ち位置として禅が生まれた。
そんな話を読みました。
だからなのか、ちょっと過激なユーモアも含まれているらしく
「シッダールタ(釈迦)の言葉をあれこれ解釈するのは
シッダールタが尻を拭いた紙を後生大事にするようなものだ」
みたいな表現さえあるらしいです。
カリスマの言葉をありがたがって自らは実践しようとはしない
…そういうのはどの分野にもあるもののように見えますが、
仏教の伝統の中にもあった話なんでしょう。
と同時に、禅にこのようなスタンスが表れるのは
言葉では理解できないところを伝えようとするからでもあるようです。
言葉を通してでは、どうしても頭で知的に理解しようとしてしまう。
もっとストレートに、言葉以外の部分で伝授していく部分が大きい。
だからこそ頭で考えようとしても無理のある禅問答を出したり、
言葉を止めて座るなかで体得していく座禅をしたりする、と。
この辺もコミュニケーションのトレーニングで重要になる部分だと感じます。
言葉ではないところで伝わるものが大きな違いを生みます。
しかしながら、言葉ではないところでの伝達は
それ相応の関係性やトレーニング量が関わるのでしょう。
ある程度の覚悟が必要なようです。
気軽に学んで、すぐに自分の課題が解決して、悩みのない日常に戻る…
そういう種類のものではありません。
そこで面白いのが、禅宗で修行の道に足を踏み入れるときには
儀式として「一度、断られる」ステップが入る、ということ。
覚悟を試すとも言えますし、心理学的には
修行のコミュニティに入るための通過儀礼だともいえます。
よく芸人や落語家が弟子入りするときに
師匠の家の前で一日中待っている、なんて話がありますが
断られても「そこを何とか」と粘るような時間を体験するらしいんです。
もちろん、このハードルの高さが修行を続ける覚悟を磨くにも役立つのでしょうし、
弟子をある程度は選抜するような効果もあるのかもしれません。
ただ僕の印象としては、それ以上に
そこまで大変な思いをしなくても大丈夫じゃないか?
と示唆してくれている部分もあるように感じました。
修行の末に苦しみから解放されるとしても、
いずれは何かしらの形で日常に戻っていくわけです。
だったら早いうちに苦しみを楽にして日常に戻ったって良いだろう。
わざわざ大変なところにいかなくても良いのでは?
そんな配慮も含まれているような気がしました。
やみくもに広げようとするのではなく、教えが必要な人に届くようにする工夫。
そのあたりにも「教える・伝える」立場として学ぶところがあるように感じています。